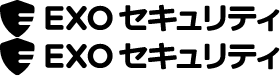


デジタル化の進展に伴い、情報セキュリティは企業経営にとって避けて通れない重要課題となりました。しかし現状、多くの企業が「セキュリティ人材不足」という深刻な問題に直面しています。サイバー攻撃が巧妙化・多様化する一方で、それに対応できる人材は決して多くはありません。
本記事では、国内外で顕在化している人材不足の実態や、その背景、さらに組織が取るべき解決のアプローチについて解説します。
サイバー攻撃のリスクは年々拡大しており、情報漏洩やランサムウェア被害といった事件は日常的に報道されています。こうした状況のなかで、セキュリティ人材の不足は国内外で共通する大きな課題となっています。
ここでは、その実態と組織への影響を見ていきましょう。
経済産業省が公表した検討会取りまとめ資料では、日本国内で約11万人ものセキュリティ人材が不足しているとする民間調査結果もあるようです。特に中小企業では専任のセキュリティ担当者を配置できないケースが多く、システム管理者が兼任して対応している状況です。
その結果、専門的なノウハウが不足し、攻撃に対して脆弱な体制のまま事業を継続せざるを得ないという問題が浮き彫りになっています。
参考:経済産業省 「「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」を公表しました」
人材不足は日本に限った話ではありません。米国や欧州でも、サイバーセキュリティ人材の需要は供給を大幅に上回っています。例えば、世界最大のサイバーセキュリティ専門家資格の非営利団体であるISC2は、世界中でみると400万人のサイバーセキュリティ人材が不足していると報告しています。グローバルに進出する企業にとっては、この人材獲得競争は避けられない課題です。
人材不足は単なる数の問題ではなく、企業活動に深刻な影響を与えます。セキュリティ監視や脆弱性管理が追いつかず、潜在的なリスクが放置されるケースも珍しくありません。また、インシデント発生時の初動対応が遅れれば、情報漏洩や業務停止の被害は拡大し、取引先や顧客の信頼喪失につながってしまいます。
セキュリティ人材が慢性的に不足している背景には、いくつかの要因があります。
ここでは教育環境からキャリアパスに至るまで、人材育成が難しい理由を整理していきます。
日本では、大学や専門学校におけるセキュリティ専門教育が十分に整っていないのが現状です。
多くの人材が企業に入社後にOJTで知識を補う形となり、即戦力の育成が追いついていません。
その結果、市場に供給される人材は限られ、人材不足が慢性化しています。
セキュリティ人材には幅が広く深い知識が求められます。例えば、ネットワーク、OS内部、暗号、アプリケーションセキュリティ、クラウド、フォレンジック、ログ解析、法令・コンプライアンスなど多岐にわたります。
さらにインシデント時は技術だけでなく、関係者との調整や経営層向けの報告など非技術的スキルも必要になります。
クラウドネイティブ、コンテナ、IoT、サプライチェーン攻撃、AIを悪用した攻撃など、技術環境や攻撃の手口は年々多様化しています。これにより、今日時点での最適解が来週には陳腐化しているかもしれず、習得した知識を継続的にアップデートしていかなければなりません。
その結果、現場は常に学習を続ける必要があり、人的リソースの維持が難しくなります。
セキュリティ人材は高いスキルを必要としますが、給与水準やキャリア形成の見通しは必ずしも十分ではありません。高度な専門性を持っていても、経営層や専門職として適切に評価されないケースが多く、結果的に優秀な人材が他社や他分野、海外に流出する要因となっています。
セキュリティ人材不足は、単なる採用強化だけで解決できる課題ではありません。むしろ重要なのは、長期的な人材育成と、組織全体でセキュリティを強化する体制づくりです。
ここでは、企業が実践できる具体的なアプローチを解説します。
既存社員に対して教育やリスキリングの機会を提供することは、人材不足を補う第一歩です。社内研修や資格取得支援だけでなく、OJTによる実践的な経験や、社外セミナー・オンライン講座への参加を推奨することも効果的です。
さらに、IT部門に限らず全社員が基本的なセキュリティリテラシーを持つことで、組織全体の防御力を底上げできます。
フリーランスや専門企業と契約し、必要な時期に外部の専門家を活用する方法もあります。特に、脆弱性診断やフォレンジック調査など高度なスキルが求められる分野では有効です。
ただし、外部に頼りきるとコスト増やノウハウの社外流出につながる恐れがあります。外部人材と協働する際には、得られた知見を社内に共有・蓄積する仕組みを整えることが大切です。
SOC(セキュリティオペレーションセンター)の外部委託や、マネージドセキュリティサービスの導入は、人材不足を補う現実的な選択肢です。自社で24時間365日の監視体制を構築するのは困難ですが、専門ベンダーを活用することで迅速な対応が可能になります。
ただし、ベンダー任せにしすぎると自社に知見が蓄積されず、判断力を欠くリスクがあるため、自社で一定の知識やモニタリング体制を維持することも必要です。
近年ではAIを活用したセキュリティ監視や脅威検知の技術が進化しています。AIが大量のログやトラフィックを解析し、異常を早期に検出することで、人材の負担を大幅に軽減できます。AIはあくまで人材を補完する存在ですが、活用することで少人数でも高いセキュリティ水準を維持できるようになります。
人材不足解消には、短期的な対策にとどまらない長期戦略が必要です。経営層がセキュリティを経営課題として位置づけるとともに、人材が定着しやすいキャリアパスや評価制度を整備することが重要です。
さらに、働きやすい環境を整え、社員が安心してスキルアップに取り組める風土を育むことが、持続的な人材確保につながります。
セキュリティ人材不足は、企業規模や業種を問わず多くの組織が抱える共通課題です。その背景には、高度な専門性の要求や教育環境の不足、待遇面の課題など、複合的な要因があります。しかし、社内教育や外部人材活用、アウトソーシングやAIの導入といった多角的な取り組みを進めることで、人材不足の影響を軽減することは可能です。
重要なのは、採用のみに頼らず、組織全体でセキュリティを重視する文化を根付かせることです。
経営層から現場社員までが一体となり、長期的な人材育成に取り組むことで、企業は持続的なセキュリティ体制を築いていくことができるでしょう。